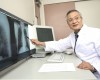手技小辞典
- 循環器科でわかる心臓マッサージ
- 心臓発作で突然倒れてしまった人を助けるとき、人工呼吸と心臓マッサージを繰り返すことが良いといわれていましたが、ここ最近では循環器科での心臓マッサージだけでも十分な処置ができることがわかってきました。心...すべて読む
- 喉頭ファイバーについて
- 喉頭ファイバーとは、喉頭がんの有無などを調べるための検査方法です。喉頭がんとは、舌の付け根から気管の入り口までの部分に発症するがんであり、呼吸や食物等の飲み込みに障害をきたしてしまうものです。喉頭ファ...すべて読む
- マクマレーテストについて
- マクマレーテストとは、筋骨格系において機能障害をきたしている部位やその症状を、特に専門的な医療器具を使用せずに手で行う検査のひとつで、主に半月板損傷または断裂のチェックを行うものです。 検査方法として...すべて読む
- ファレンテストについて
- ファレンテストとは、手根管症候群かどうかを確認するためのものです。手根管症候群とは、簡単にいうと手のしびれが起きる症状です。主に人差し指や親指などの指先でしびれや痛みを感じます。これは、手の平と手首の...すべて読む
- 乳房温存手術について
- 乳房温存手術とは乳がん患者に用いられる手術法で、乳房全体を摘出しなくてもいいという理由から日本人患者の3分の2がこの乳房温存手術での治療を受けています。 乳房温存手術の長所としては切除部分が大きくがん...すべて読む
- 不整脈カテーテルの検査・治療方法
- 不整脈という症状には健康被害がないものから死に繋がるものまであり、もちろん健康被害があるものに対しては直ちに治療をしていかなければなりません。 今までなら不整脈=薬での治療といった方法が一般的とさせて...すべて読む
- 血行再建術
- 血行再建術には2種類あります。1つは、動脈硬化などで血管の内側が狭くなることで詰まったり、流れが悪くなったりした血柱内膜をとる血中内膜剥離術です。もう1つは、狭くなったり閉塞してしまったりした動脈に対...すべて読む
- ブラガードテスト
- ブラガードテストとは、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛を調べるための検査の一つです。ブラガードテストをする前に、先に膝関節を伸ばしたまま、股関節を曲げて足を持ち上げる下肢伸展挙上テストという検査をして、痛み...すべて読む
- 坐骨神経痛を調べるラセーグテスト/ラセーグ徴候について
- ラセーグテストとは整形外科において坐骨神経痛を調べる場合に用いられる検査方法の一つです。 坐骨神経痛とは、運動や生活の中でのストレスなどが原因だとされており、さまざまな年代で発症します。症状としては仙...すべて読む
- 内視鏡的硬化療法での食道静脈瘤の治療について
- 食道静脈瘤は食道の粘膜下にある静脈が腫れているような状態になり、破裂してしまうケースがあります。 しかし、食道静脈瘤は自覚症状がほとんどない病気で、そのまま放置し、悪化してしまうと最悪吐血をし、その出...すべて読む
- アブレーション治療(循環器系)
- アブレーション治療は大腿部など、太い血管がある場所にカテーテルを挿入し、心臓にある不整脈の原因となる部分までカテーテルを到達させ、不整脈の原因となっている部分を電流で焼き切ることによって行う手術法です...すべて読む
- 冠動脈形成術(循環器系)
- 冠動脈は心臓に酸素を供給する動脈です。ストローほどの太さがあり、左冠動脈、右冠動脈の二本の主要動脈があります。冠動脈がコレステロールなどによって狭くなってしまうと血管に流れる血液量が減少し、胸の痛みや...すべて読む
- 大腸の内視鏡検査(消化器系)
- 大腸の内視鏡検査は東大の丹羽、弘前大学の松永、東北大学の山形によって機器が開発された手術法です。弘前大の田島が盲腸まで挿入する方法を開発し、さらに手術法の発展が進みました。内視鏡は肛門から挿入し、直腸...すべて読む
- 膀胱造影
- 膀胱造影とは、カテーテルと呼ばれる細い管を尿道口から挿入して膀胱の内部に造映剤を注入し、X線撮影で膀胱の形状や膀胱内の状態を調査する検査のことを指します。 一般的には膀胱炎や膀胱癌などの膀胱の病気の有...すべて読む
- 弁形成術
- 弁形成術は、心臓内の弁と呼ばれる血液逆流防止用の腱にトラブルが発生した場合の治療方法のひとつで、患者自身の弁を修復して機能を回復する心臓外科の手術です。 心臓には4つのエリアがあります。 ①大静脈から...すべて読む
- ケンプテスト
- ケンプテストとは整形外科学的検査のひとつで、機械や道具を用いずに患者さんの症状から判断し、身体を捻ったり曲げたり、関節を圧迫したりする事で原因を見つける検査方法です。正確な診断のため他の検査と組み合わ...すべて読む
- 人工骨頭挿入術
- 人工骨頭挿入術とは、大腿骨頭壊死や大腿骨頚部骨折の不安定型と呼ばれるタイプの複雑骨折、高齢者の大腿骨骨折の等、骨接合術で整復・固定が困難な場合や早期荷重が必要な場合に、大腿骨の骨頭を取り出し人工骨頭(...すべて読む
- 下肢静脈瘤レーザー治療
- 下肢静脈瘤レーザー治療に用いられるレーザーの機種は、レーザー治療開始当初に比べ、とても進化しています。様々なレーザー機種がある中で、それぞれの機器に高い血管処理能力があるので、医師による診断の能力や技...すべて読む
- 塞栓術
- 塞栓術とは、肝臓癌に対して行われることが多い治療法で、肝動脈塞栓術と呼ばれています。この塞栓術は、癌に栄養や酸素を送っている血液の流れを人工的に止め、癌を壊死させるという治療法で、動脈塞栓術や血管塞栓...すべて読む
- 光線力学療法
- 加齢黄斑変性は、網膜の中心部に起こる異常のため、よい治療法を見つけることができませんでした。 しかし、2004年5月に、病変部だけにレーザーを照射することを可能にした、光線力学療法が開発され、認可され...すべて読む
- 内視鏡下副鼻腔手術
- 内視鏡下副鼻腔手術とは1980年代に日本に紹介され、1990年代になると急速な普及を果たした内視鏡を使用した手術方法です。ESSと称される場合もあります。 従来の鼻根本手術は口内の歯茎の上部を切り開き...すべて読む
- アドソンテスト
- アドソンテストは胸郭出口症候群の判別のために用いられる検査方法です。胸郭出口症候群の中でも特に斜角筋症候群の判定を行うのに適しています。 アドソンテストの検査は ①姿勢良く座った状態で手首の脈拍を確認...すべて読む
- PELD/経皮的内視鏡下腰椎間板ヘルニア摘出術
- 経皮的内視鏡下腰椎間板摘出術(以下PELD)は新しい椎間板ヘルニアの手術として注目を集めています。PELDは1975年にその施術につながる技法が考案され、1980年代になると病変部位を観察しながら摘出...すべて読む
- TLIF/片側進入腰椎後方椎体間固定術
- 片側進入腰椎後方椎体間固定術(以下TLIF)は左右どちらかの椎間関節を切除して椎間板を摘出し、その後に固定手術を行う手術法です。 経椎間孔進入椎体間固定術とも言われおり、椎間板ヘルニアや腰椎変形すべり...すべて読む
- ストリッピング手術
- 下肢静脈瘤は下肢の血液が血管に溜まることにより血管(静脈)が浮き出てきたり、こぶのように膨らんでしまう病気です。足がむくむ・こむら返りを起こすなどの症状もみられます。 良性疾患のため命にかかわるような...すべて読む
- 低侵襲手術
- 医学用語の侵襲とは病気や怪我、手術などの医療処置で生体を傷つけることを言います。医療行為を行う場合、大きな負担を伴う手術だけでなく、採血やレントゲン撮影、投薬などを行う場合にも生体を傷つけてしまいます...すべて読む
- 残尿測定について
- 排尿困難や、尿閉などのケースで心配なのが残尿です。残尿があると感染症や結石のほか、脊椎損傷、パーキンソン病、椎間板ヘルニア、糖尿病、前立腺肥大症および前立腺がん、排尿筋協調不全など様々な病院の原因とな...すべて読む
- 脊椎固定術
- 脊椎が重労働やスポーツなどにより疲労骨折を起こす脊椎分離症、怪我による椎骨の骨折や脱臼のため脊椎が不安定な状態になる脊椎骨折、その他にも椎間板年、脊椎腫瘍、脊椎カリエスなどの疾患に対し脊椎固定術が施さ...すべて読む
- MAZE手術または心房細動手術
- MAZE手術(心房細動手術)は心房内に不規則な興奮が生じけいれん状態を起こす状態にある方に対し行われます。この不整脈は死亡に至らしめる危険なものではないものの脈の規則性や収縮が無くなることにより、心臓...すべて読む
- 弁置換術
- 弁置換術は、心臓弁膜症の外科的治療法の一つで、患者さんの悪くなった弁を取り除き、新しく人工弁と呼ばれるものを同じ位置に縫着し置き換える手術です。 手術は全身麻酔を用いて行う手術です。弁置換術は、開胸し...すべて読む

おすすめ記事
- SLRテスト‐別名:下肢伸展挙上テスト
- SLRテストは、坐骨神経痛か股関節痛かを決断するために行われる方法です。
腰の痛みに関係する病気はとてもたくさんあるため、病気を特定することが困難な場合がある事があります。特に、股関節痛は坐骨神経痛と似た症状を起こす病気として挙げられています。このSLRテストが陽性の結果であれば、坐骨神経痛で陰性の結果であれば股関節痛と判断されています。
このテストの方法は、痛みのある方に上向きに寝て...すべて読む
- 骨折観血的手術について
- 骨折観血的手術は、ギプス固定では治癒が難しい複雑な骨折や重度の骨折、関節周辺を骨折した場合に施す外科手術のことをいいます。
1895年にX線が発見され、骨折部分の状態がわかるようになったことで、これまでの外科的手術を施さない非観血的手術に代わって、20世紀のはじめには骨折観血的手術が報告されています。骨折観血的手術は主にヨーロッパで行われ、その後、移植骨を用いて骨を整復する技術が確立されると...すべて読む
- 坐骨神経痛を調べるラセーグテスト/ラセーグ徴候について
- ラセーグテストとは整形外科において坐骨神経痛を調べる場合に用いられる検査方法の一つです。
坐骨神経痛とは、運動や生活の中でのストレスなどが原因だとされており、さまざまな年代で発症します。症状としては仙髄神経の中でもS1、2、3、または腰髄神経のL4、5の神経が圧迫されている状態で、ラセーグテストではその場所に負担をかけ、異常が無いかを検査していきます。
ラセーグテストの方法としてはとても簡...すべて読む
- アレンテスト
- アレンテストは、麻酔時、動脈の穿刺を行う際に、腕の動脈が閉塞していないかを調べるためのテストです。
麻酔をかける際、腕の親指側にある橈骨動脈または小指側にある尺骨動脈に動脈ラインを入れますが、どうしても動脈ラインを入れた動脈の血流は悪くなります。その間、指尖部への一定の血流を保つためには、動脈ラインを入れていない方の動脈が閉塞してないことが絶対条件となります。
もし、橈骨動脈、尺骨動脈...すべて読む
- 神経学的テスト:スパーリングテスト
- スパーリングテストとは神経根障害を調べる神経学的テストです。
頚椎は7つの骨が積み上がってできていますが、その後ろを走る脊髄から枝分かれして上肢にいく神経が椎体と椎体間の椎間板の部分に伸びた末梢神経を神経根といい、この神経根に異常があるかを確認するテストがスパーリングテストというわけです。
スパーリングテストは徒手検査法において、機械を使わない検査法です。脊髄の実質の症状である脊髄症状...すべて読む
- マクマレーテストについて
- マクマレーテストとは、筋骨格系において機能障害をきたしている部位やその症状を、特に専門的な医療器具を使用せずに手で行う検査のひとつで、主に半月板損傷または断裂のチェックを行うものです。
検査方法としては、まずその疑いがある患者を仰向けにさせます。そのままの体勢で膝を最大限に曲げ、足の底と関節を手で持ちます。そのままゆっくりと下腿を外旋、内旋させながら、そのときに生じる痛みなどで診察をします。(補...すべて読む
- ジャクソンテストの方法
- 頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などという傷病名は、一般的にむち打ちと呼ばれるもので、交通事故の衝撃によって首が大きく前後に動き、その結果として痛みが生じた場合、後遺障害として評価の対象となります。
その神経根障害を調べる神経学的テストがジャクソンテストで、これはスパーリングテストと同様に椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などを調べる代表的な検査となります。
ジャクソンテストの検査方法...すべて読む
- ケンプテスト
- ケンプテストとは整形外科学的検査のひとつで、機械や道具を用いずに患者さんの症状から判断し、身体を捻ったり曲げたり、関節を圧迫したりする事で原因を見つける検査方法です。正確な診断のため他の検査と組み合わせ、必要なら画像診断をする事も必要です。
このケンプテストは、椎間板の損傷、椎間板ヘルニア等による神経根の圧迫が椎間板内側部にあるか椎間板外側部にあるかを確認する検査方法です。
原理として旋回...すべて読む
- ブラガードテスト
- ブラガードテストとは、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛を調べるための検査の一つです。ブラガードテストをする前に、先に膝関節を伸ばしたまま、股関節を曲げて足を持ち上げる下肢伸展挙上テストという検査をして、痛みが出たところから五度角度を下げます。その状態で足の関節を背屈させることで坐骨神経のさらなる伸展を行った時に、痛みやしびれが増すと陽性と判定されます。
この際、ハムストリングスやアキレス腱などの緊...すべて読む
- 後期研修医の給料
- 近年は少子化、高齢化にともなって、医師不足も深刻な問題となっています。
医師を目指す若者が減っている一方で、熱心に勉強を重ね、医師を目指す若者も少なくありません。医師を志す若者が、仕事の時間ならびに給料についても気になるところです。
医師になるにあたっては、研修があり、その点では、前期研修医と後期研修医に分けられます。大学を卒業して2年間を前期研修医、その後の3年目からを後期研修医と呼びま...すべて読む
コラム内から検索