医師のオンコールは労働時間にならない?法的観点から徹底解説【荒木弁護士解説】
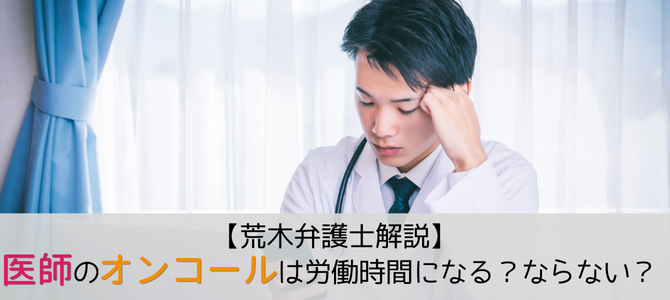
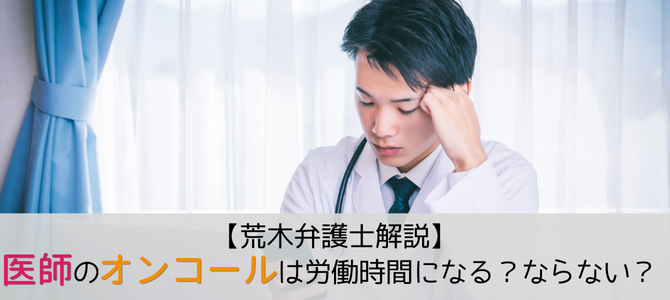
医師転職研究所が2023年12月に医師1746名を対象に実施したアンケートでは、週5日以上病院に勤務する医師のうち3分の2以上の医師がオンコールを担当しているという結果がでています。

診療科や病院の種類によっても割合は大きく変わると思いますが、病院の常勤医として勤務する場合は、オンコール当番の有無、有の場合はその頻度や内容は、勤務医のQOLにかかわる重要なポイントだと思います。そのため、オンコールの負担が転職の理由となったり、オンコールの有無が転職先を決める要素の1つにもなったりするのではないでしょうか。
宿直(当直)・日直については、上限が設定されており、宿直は原則週1回、日直は月1回とされています。(昭和22年9月13日付け発基17号)しかし、オンコールについては、このような回数の上限等も定められておらず、回数(頻度)や内容も病院や科毎に様々であるというのが実際です。
また、従前より医師の世界においては、患者の主治医になれば、休日深夜問わず最後まで責任をもって診るという考えがあったかと思います。そのため、オンコール当番制が敷かれているか否かに関係なく、担当患者に急変等の異常があれば病院から連絡が来て、休日深夜でも主治医が対応に当たることが一般的だったのではないでしょうか。
オンコールは病院の常勤医の多くが担当する一般的な制度であるにもかかわらず、これまで医師のオンコールの労働時間性というその法的性質が議論されることは少なかったのは、このように医師の職業倫理から当然のこととして受け入れられてきたことによると考えます。
しかしながら、2024年4月からスタートした医師の働き方改革に関する議論の中で、医師のオンコール制度についても議論がされ、また医療従事者のオンコール当番の労働時間性が争点になった裁判例も複数出ています。
また、QOLを重視する働き方を希望する医師にとっては、呼び出しがあるか否かなどオンオフがはっきりせず、対価性を欠くことが多いオンコール当番は敬遠される傾向があると感じています。
今回は、これまであまり議論されていないオンコール当番の法的性質について解説したいと思います。
オンコール当番の内容は、病院毎に内容が異なる場合や、手術を行う科の場合には手術待機など科によっても特徴があります。先ほどご紹介した医師転職研究所が実施したアンケート結果でも電話と呼び出しの両方があるもの、電話はかかってくるが呼び出しが少ないもの等その内容や頻度にもばらつきがありました。

筆者が知るケースでは、緊急手術の際に出勤する手術待機(呼出のみで、電話対応はなし)や病棟や救急外来からの電話相談がメインで呼び出しはほとんど無いケース、救急隊から直接電話のあるホットラインの対応をするケースなどがあり、オンコール当番と一口に言ってもその内容は様々でした。
更に、土日祝日のオンコール当番になった場合は、朝や夕方に病棟回診を行う事実上の院内ルールがあるなど、病院毎、科毎のローカルルールの存在も見聞きします。
病院常勤医師のオンコール待機手当の額についても筆者が知る限りにおいては、支払われないか支払われても数千円という少額の手当の場合が多いように思います。中には1万円以上の待機手当が支払われるケースも聞いたことがありますがそのようなケースは少数だと思います。
オンコール待機中に呼び出しを受けて実際に院内で勤務した時間やオンコール待機中に電話がかかってきて電話対応した時間は労働時間となりますが、オンコール待機時間は労働時間となるのでしょうか。
医療従事者のオンコール待機時間の労働時間性が問題になった裁判例をご紹介したいと思います。
旧県立奈良病院に勤務する産婦人科医師2名が病院を運営する県立病院機構に対して宿日直勤務中及び宅直当番の待機中の時間外手当を請求した事案です。
職種・診療科:産婦人科の医師
宅直当番の内容:
宅直当番が労基法上の労働時間に該当するか否かについては、「実作業に従事していない時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が非従事時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。」という最高裁判決の基準(三菱重工長崎造船所事件/最高裁平成12年3月9日)を示したうえで、
等の事情に照らして、
「宅直当番を担当している医師は,産婦人科医師らの申合せに従って,宿日直担当医師その他本件病院の職員から連絡があった場合には直ちにその指揮監督下に入ることができるように努めていたとは認められるものの,それを超えて,宅直当番の全時間について病院長の指揮監督下にあったと評価することまではできない。」と判示して、待機時間を含めた宅直当番の全時間の労働時間性は否定されました。
訪問看護ステーションに勤務する看護師の緊急看護対応業務のための待機時間が労働基準法上の労働時間であるとして未払の時間外手当を請求した事案です。
職種・診療科:訪問看護ステーションに勤務する看護師
緊急看護対応業務の内容:
労働基準法上の労働時間について、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない不活動時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。」という最高裁判例の基準を示したうえで、
等の事情に照らして、
No1の携帯電話機を所持して緊急看護対応業務を担当した日は、その業務に従事した時間はもとより、待機時間も含めて被告の指揮命令下に置かれていたものであり、これは労働基準法上の労働時間に当たるというべきであると判示し、オンコールの待機時間も含めて労働時間と認定されました。
形成外科の専攻医であった医師が病院を運営する法人に対してオンコールの待機時間も含めて労働時間であるとして未払残業代等を請求した事案です。
職種・診療科:形成外科の専攻医
オンコール当番の内容:
裁判所は、オンコール当番日において本件病院外で待機している時間が全体として労働時間に該当するか否かについて
・オンコール当番としての対応
形成外科のオンコール当番は、形成外科所属医師以外の医師が外科の当直をしている際、形成外科の専門性が高い変化が患者に生じた場合に、当直医等から問合せを受けて、その処置の方法等を説明し、場合によっては出勤して処置等を行い、あるいは切断指ホットラインに対応するといった、緊急性の比較的高い対応のみが求められていた。
・オンコール当番中の電話対応及びこれに要する時間
当直医からの問合せは、電話により方法を説明できる程度の処置の内容を説明するものであり、切断指ホットラインは、切断指患者の基本情報等についての救急隊の応答を踏まえて、本件病院から遠方又は外傷が軽微な場合は本件病院での受入れは拒否し、それ以外の場合は上級医に相談した上で救急隊に受け入れる旨の回答をするなどにとどまるから、いずれも長時間の対応を要するものではない。
・電話対応や出勤が求められた回数等
院外におけるオンコール待機中の架電は、平日のオンコール当番4回のうち架電がないことが1回程度あり、それ以外は当番1回につき1回以上の架電があり、日曜・祝日のオンコール当番時は、病院外で毎度複数回、架電があるにとどまるから、オンコール当番時間の長さに比して電話対応の回数が多いとはいえない。
切断指ホットラインも、切断指症例自体が比較的珍しく、切断指患者が本件病院のある千葉県以外の隣接都県からも搬送されることを考慮しても、原告の退勤後から翌日の出勤までの間に切断指患者の受入れ如何を判断しなければならない事態が頻繁に生じていたとは考え難い。
原告が病院在職中、39回オンコール当番を担当した中で、院外で待機している際に架電に応じて出勤した回数は7回であって、すべて日曜・祝日のオンコール当番中の出勤であり、1回のオンコール当番で出勤することがあったとしてもその回数は1~2回にとどまっている。
出勤した場合の勤務時間は、9時間11分と長時間になったことが一度あったものの、それ以外は1時間24分から3時間45分であり、オンコール当番医が出勤して勤務する時間としては比較的短時間にとどまっている。
等の事情からオンコール待機時間中に出勤を余儀なくされても、院外における原告の私生活上の自由時間に多大な影響を及ぼすということはできない。
と判示し、オンコール待機中の労働時間該当性については否定されました。
まず、オンコール当番中に実際に電話対応をした時間と実際に病院に出勤して勤務した時間が労働時間に該当することは医師及び病院との間で争いがありませんでした。
この病院では、オンコール当番の医師が形成外科の入院患者の朝・夕の回診を行うこととされていたため原告となった医師もオンコール当番の日に回診のために出勤していましたが、この出勤時間については当然に労働時間となりました。
しかしながら、院外でのオンコール待機時間中の労働時間については、否定されました。⑵で紹介したアルデバラン事件では原告の訪問看護師のオンコール待機中の出勤頻度16.4回に1回でしたが、元形成外科の専攻医の場合は5.6回に1回と訪問看護師のケースよりも頻度が高く、両判例を統一的に理解することが難しいと思います。
他方で、医療従事者のオンコール当番の内容・頻度は様々であり、裁判例の蓄積もまだまだ少ないため今後の裁判例等の出現による議論の状況に着目していきたいと思います。
放射線技師のオンコール待機手当に関して興味深い裁判例がありましたのでご紹介いたします。
東京都内の医療センターに勤務する放射線技師である原告が医療センターを運営する法人に対してオンコール待機時間が労働時間であるとして2019年10月から2021年3月分の間の未払賃金約1700万円とこれに対する遅延損害金を請求した事案です。
本センターに所属する放射線技師は、原告を含めて2名であり、それぞれ月15日程度オンコール待機をしており、原告の出勤頻度は月3回程度でした。また、特別手当(オンコール手当)として月額2万円が支払われていました。
本訴訟の判決文によると、本訴訟の前に原告である放射線技師は、2016年10月1日から2019年9月30日までの間におけるオンコール待機期間に対応する未払賃金額として約2400万円を請求する訴訟(前件訴訟)を提起し、2021年6月に被告である法人が原告である放射線技師に対して500万円の解決金を支払うという内容の裁判上の和解が成立していたとのことです。
訴訟は、判決にまで至らずに裁判上の和解で終了することのほうが一般的で、実際に労働事件に関する訴訟(第一審)では、約60%が和解で終了しています。(令和5年司法統計年報1民事・行政編参照)
もっとも、裁判上の和解をする際には、守秘義務条項が設けられることが一般的なため、和解内容やその金額が公になることはあまり無く、そのような訴訟が存在したこと自体第三者が知ることが難しいのが実際です。
そのため、本訴訟の判決文に記載のある放射線技師が月の半分のオンコール当番待機期間中の3年分の未払賃金を請求して500万円の解決金を医療機関が支払うという和解が成立したという事実は着目すべき点であると考えます。
なお、本訴訟で請求する未払賃金については、前件訴訟での和解の際の清算条項により清算済みで存在しないとして原告の放射線技師の請求は認められませんでした。そのため、本訴訟では、原告の放射線技師のオンコール待機(月15日、3回程度出勤)の労働時間性については判断していません。
いかがでしたでしょうか。これまで医療従事者のオンコール当番については、労働時間性も含めてあまり議論がされて来ませんでしたが、医師の働き方改革の一連の議論の中で医師のオンコール当番制度が着目され議論がされています。また、QOLを重視する働き方を希望するという意識の変化や近年医療従事者のオンコール当番の待機時間に関する裁判例が複数出ていることからオンコール制度や最新の裁判例についてご紹介しました。
筆者は引き続き医師のオンコール当番制度に着目していきたいと考えておりますので、本記事のアンケートフォームから本記事の感想やご自身のオンコール当番の内容(頻度、対応内容、手当の有無・額)やその負担についてお寄せいただけますと幸いです。
他の記事を読む